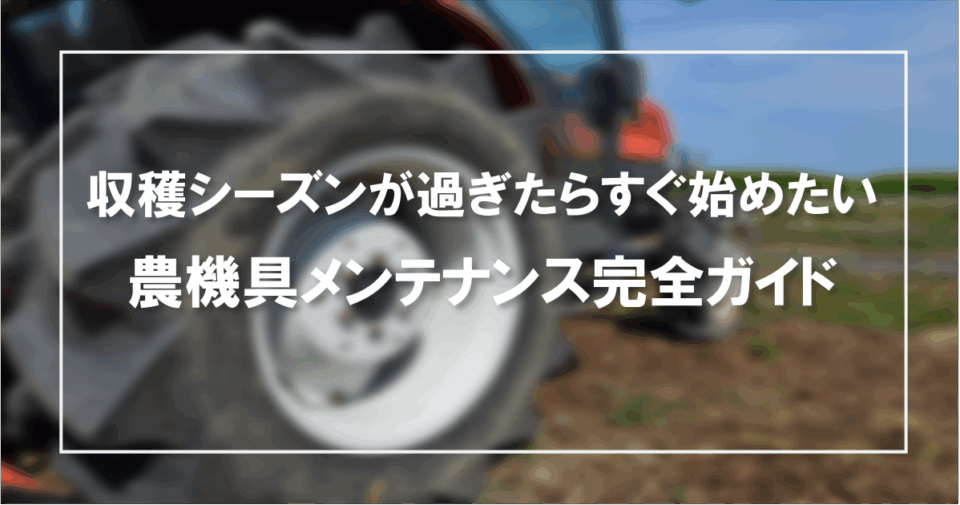
2025.11.03
収穫シーズンが過ぎたらすぐ始めたい、農機具メンテナンス完全ガイド
1.なぜ“収穫後のメンテナンス”が重要か
稲刈りや秋作、果樹の収穫など、農業にとって一年の中でも特に農機具が酷使される時期が過ぎようとしています。収穫シーズン中はコンバイン、トラクター、乾燥機、籾摺り機など、多くの機械がフル稼働し、刃やベルト、エンジン、フィルター、駆動系など、さまざまな部品に負荷がかかります。使用頻度や稼働時間が高いため、故障のリスクも上がりますし、小さな摩耗や汚れが放置されると、翌年の始動不良や大きな修理コストにつながることもあります。
本記事では、収穫シーズン後に行っておくべきメンテナンスのチェックポイント、整備・部品交換・潤滑・保管のコツ、そして“プロに任せるべき領域”などを解説します。農家の皆様が「来年も安心して使える農機具」を手に入れるためのお手伝いになれば幸いです。
2.収穫期に酷使される部位と起きやすい故障・トラブル例
まず、どの部分が収穫期に特に使われるか、そしてどのような摩耗や欠損・故障が起きやすいか把握しておきましょう。
| 農機具 | よく使われる部位 | 起きやすいトラブル・故障例 |
| コンバイン | 刈取部(刃、ナイフ・バリカン部)、 脱穀部(こぎ胴・揺動板)、 殻粒選別部、排わら処理部、 足回り(クローラ、転輪) | 刃の摩耗・切れ味低下、ベルトの緩み・亀裂、籾殻詰まり、揺動板のゆるみ、排わら処理部の刃欠け、足回りの磨耗や亀裂、バッテリー上がり、電気系統の断線 |
| トラクター | エンジン・燃料系、 オイルフィルター・エアクリーナー、駆動ベルト・プーリー、油圧系・クラッチ・ブレーキ、足回り・タイヤ | オイル劣化、フィルター目詰まり、ベルト滑りや切断、クラッチ焼け、ブレーキ引きずり、タイヤ空気圧異常、油漏れ、ゴム部品のひび割れ |
| 乾燥機・籾摺り機 | 燃焼部・バーナー、乾燥ファン・送風ダクト、排塵ダクト、選別ふるい、モーター・軸受 | 燃焼効率低下、異常燃焼、不完全燃焼、ファン異音・振動、異物混入、軸受摩耗、異常発熱、フィルターやふるいの破損 |
| 共通部位 | ベルト・チェーン・ギア・潤滑部、オイル類、燃料・バッテリー、電気配線、保管・洗浄状態 | 潤滑不足、錆・腐食、燃料腐敗、バッテリー容量低下、電線かじられ・断線、汚れの蓄積、保管中の湿気によるカビや錆び発生 |
こうしたトラブルは、「使用頻度」「保管状況」「清掃・洗浄の有無」によって発生率が大きく変わります。
3.収穫後~オフシーズンにかけての基本メンテナンス
以下のチェックリストをもとに、「自分でできる点検・整備」「潤滑・消耗品の交換」「保存・保管」を体系的に行いましょう。
A. 洗浄と清掃(洗浄・汚れ除去)
- 使用後すぐに泥・藁・籾殻などの付着物をブラシ・高圧水などで洗い流す。
特に刈取部・排わら処理部・脱穀部の入り組んだ場所。 - 機体内部のゴミや虫、ネズミなどの住みかになりやすい隙間部分の確認。電線の被覆がかじられていないかなどの点検も含める。
- 洗浄後は金属部の水分をしっかり取り、乾燥させてから保管場所へ。錆びや腐食の発生を防ぐため。
B. 点検・整備(点検・整備・部品交換)
- エンジン管理:オイルの交換または補充、オイルフィルターやエアクリーナーの清掃または交換、燃料フィルターの確認。使用説明書に沿ったオイル粘度・品種を選択すること。
- 駆動系・伝動部:ベルト・チェーン・クラッチ・プーリーなどの張りや摩耗状態のチェック。必要があれば交換。ギアオイルやグリースの注油。クラッチ・ブレーキ系のリンク部/ワイヤー部への潤滑。
- 刃・切断部の刃物:刈取部・排わら処理部の刃の切れ味、欠けや曲がりの有無。研磨可能であれば研磨、無理なら交換。刃の調整・刈高・刈深さの設定。コンバインなどでは刈取部の刃と輸送部・排わら部の協調動作が重要。
- 足回り・走行部:クローラ、転輪、タイヤ、走行用ベルトやチェーン部分の摩耗・ひび割れ・張りの異常。走行部に付着した土の除去。空気圧調整(タイヤ車)、チェーンやクローラの張り調整。
- 乾燥機・燃焼系機械の特別点検:バーナー部の異常燃焼・燃料系の詰まり・燃料タンクの錆/汚れ・送風・排塵ダクトの詰まりや折れ、ふるい・選別系の網・ふるいの破れや変形。温風路や排風路の掃除。水分計の校正。
C. 保存・保管・保護(保管・腐食防止)
- 保管場所は 日陰で風通しが良い 所。湿気を避ける。屋根付き、壁付きが可能なら壁側も風がこもらないようにする。
- 金属部に防錆剤を塗布したり、油膜を残すことで錆の進行を抑制。可動部分には潤滑油・グリースの注入。
- 燃料タンク内の燃料残留がある場合、燃料劣化やタンク内腐食の原因となるので、可能なら抜くか、燃料安定剤を添加。バッテリーは満充電に近い状態で保管、必要があれば定期的に充電。
- カバー等で機体を覆う、湿気やホコリを防ぐ。使わない部品・工具は整理・片付けておく。部品・交換パーツの備え(ベルト・刃など)を確保しておくと、急な破損時に対応しやすい。
D. 安全・記録・チェック表
- 点検・整備を行う際は必ずエンジンを停止。火気・可動部・安全カバーの確認。保護具(手袋・安全靴など)を使用。
- チェックリストを用いて定期点検を実施、記録を残す。どの部品がどのくらい摩耗したか、いつ交換したかを記録しておくと、コスト管理にも役立つ。
- 取扱説明書・メンテナンスマニュアルをよく読むこと。「使用頻度」「推奨交換時期」「潤滑種類」など、機種・メーカーごとの指示に従う。
4.なぜこのタイミングでやるべきか:メリットとコスト比較
収穫後~オフシーズンにかけて早めに整備を始めることには、以下のようなメリットがあります
- 翌シーズンの「始動不能・故障」での時間ロスを防げる
→ 作業計画が崩れることによる収穫遅延や品質低下を回避 - 故障が小さいうちに発見・修理すれば、修理コストが低く済む(部品交換だけで済むなど)
- 整備がきちんとしていることで、査定額アップ
→ 将来的な買い替え・機種入れ替え時に有利になる - 機械寿命の延長
→ 新規購入コストを抑えられる、投資回収がしやすくなる - 安全性が向上
→ 作業者の事故リスクが減る(可動部・刃・駆動部などによるケガ防止)
一方、整備・交換・部品調達・潤滑油・交換費用などのコストもかかります。しかし、これを「コスト」ではなく「投資」と考えると、“メンテナンスコスト vs 故障時コスト・ダウンタイムコスト”の比較で、前者の方が少ないケースがほとんどです。
5.プロに任せるべき部分と自分でできる範囲
すべてを自分で行うのは難しい・危険を伴う部分もあります。以下に“自分でできる範囲”と“プロに依頼すべき範囲”を整理します。
| 自分でできること | プロに依頼すべきこと |
| 洗浄・汚れ除去、ホコリ・籾殻などの付着物除去 | 複雑な機械内部・脱穀部・選別部の微細な部品の修理・交換 |
| 刃や刈刃の摩耗チェック、簡単な研磨 | ベルト・チェーンの本格交換、駆動伝動系の調整・整備 |
| オイル・フィルター類の交換(初心者でも取説通りなら可能なもの) | エンジン内部の修理、燃焼調整、電気系統(センサー・配線)トラブル |
| 足回り(タイヤ・クローラ・転輪)のクリーニングと簡単点検 | 足回りの構造損傷・歪み・ひび割れなど重大な摩耗の修復 |
| バッテリー管理・充電 | 専門工具が必要な分解整備や校正(たとえば、水分計校正など) |
プロに依頼した場合の費用・納期の目安をあらかじめ把握しておくと安心です。また、信頼できるメーカーや販売店の整備サービスを使うことで、部品純正・保証などの点で安心できます。
6.買取を考えている人向け:整備が査定に与える影響
将来的に農機具を売却・買い替えしたいと考えている場合、収穫後のメンテナンス更新は査定額を左右する重要な要素です。以下は査定をアップさせるための整備ポイントです。
- 刃やベルト、チェーンなど消耗部品の摩耗を最小限にし、切れ味・張りを良好に保っておく
- 洗浄・見た目の清潔さ:泥・錆・油染みなどをきれいにしておくことで印象アップ
- オイル漏れ・異音・振動など明らかな故障兆候がないことを確認・修理しておく
- 保管状態の良さ(風通し・湿気・錆防止など)、保管時カバーや防錆剤の使用の有無をチェックされることもある
- 記録:いつどこを交換・整備したかがわかる記録があれば、それを提示することで信頼性が上がる
こういった“整備履歴がある農機具”は、買い手・買取業者・中古市場での評価が高くなります。特にベルト・刃などの消耗品が新品または状態良好であることは大きなプラスです。
7.実際の現場から:失敗例と成功例
失敗例
- 某農家では、収穫後に刈取部の刃の摩耗を気にせず翌年を迎えた結果、稲の切り口が不揃いになり、作物の品質が落ち、刈取り速度も遅くなった。結果として「刈取部刃交換+追加部品代」で予想外のコストがかかった。
- 別の例では、トラクターの駆動ベルトが切れ、作業中に停止。代替ベルトを取り寄せるまでに数日かかり、収穫タイミングを逃した。損失が大きかった。
- 保管中に燃料タンク内に水分が入り、燃料腐敗を起こし、燃料系統のクリーニング・フィルター交換で多くの作業・コストを要した例。
成功例
- 収穫直後に「刃の研磨・ベルト調整・オイル交換・洗浄」をまとめて実施した某農家は、翌年の始動率が非常に良く、刈取部・脱穀部のトラブルがほぼゼロ。
- メンテナンス記録を付けていたことで、買い替えを検討した際、整備履歴が取引先に評価され、買取価格が他農家の機械より10〜20%近く高く評価された。
- 乾燥機のファン・排塵ダクトの掃除を怠らずに毎年実施していたことで、燃焼効率が安定。燃料消費が減り、省エネ効果にもつながった。
8.よくある質問とその答え(FAQ形式)
Q1:どのくらいの頻度で整備・点検をすればいいですか?
→ 使用頻度・作業時間により異なりますが、少なくとも「収穫後」「オフシーズン開始時」「繁忙期直前」の3回は大きな点検・整備を。使用中も可動部の異音・振動があればその都度確認を。
Q2:プロに依頼するときの費用目安は?
→ 機械の大きさ・メーカー・故障の程度によりますが、ベルト交換や刃物交換などの部分整備であれば数千円〜数万円。エンジン・燃焼系・構造的な故障だと数十万円になることも。見積もりを複数取り、整備業者の信頼性を確認しましょう。
Q3:整備部品は純正品を使った方がいいのですか?
→ 純正部品は設計通りの性能・耐久性が保証されており、整備後の寿命・安全性・査定価値において有利です。ただし、汎用部品・代替品で費用を抑えられる場合もあり、用途や予算・信頼できる代替品であるかを確認した上で判断すること。
Q4:保管場所が屋外しかない場合、どうすればいいですか?
→ 屋外保管でも、シートやカバー、防錆剤を活用して湿気・雨・直射日光を避ける。金属部の防錆・潤滑箇所の油切れを防ぐために定期的にチェックを。可能であれば、高床やパレットを使って地面との接触を避ける。
9.まとめ
収穫シーズンが終わったあと、少しゆとりができるこの時期こそ、農機具のメンテナンスをしっかり行うチャンスです。摩耗・汚れ・錆び・詰まりなどの問題は、放置すると機械寿命を縮め、コストや手間が何倍にも膨らむことがあります。「点検」「整備」「交換」「保管」のプロセスを毎年繰り返し、記録を残すことで、故障リスクを抑え、作業効率を上げ、買取・買い替えの際にも有利になります。 農機具は農家にとって大きな資産です。少しの手間を惜しまず、正しいメンテナンスを施すことで、その資産価値を維持し、次の収穫シーズンへ安心して臨むことができます。もし「手間がかかる」「どこから始めたらいいか分からない」と感じたら、まずはこのチェックリストから一つずつ進めてみてください。
プレジャーの出張買取では、出張買取にかかる手数料・査定料がすべて無料です。
査定金額にご満足いただけない場合は、その場で無料キャンセルも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください!

