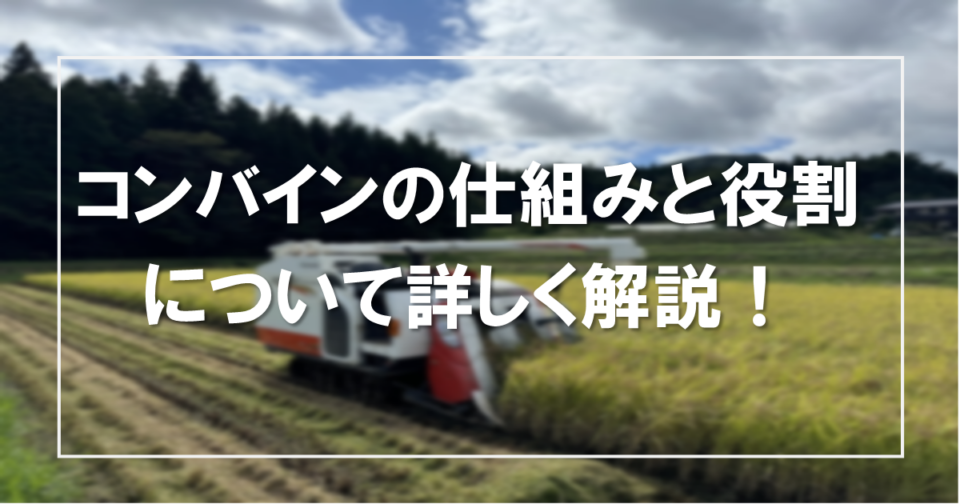
2025.02.25
コンバインの仕組みと役割について詳しく解説!
コンバインは農業において、刈取り・脱穀・選別の作業を一台で行うことができる非常に効率的な機械です。短時間で多くの収穫物を処理できるうえに、籾の取りこぼしを最小限にする機能も備えており、農作業の生産性向上に大きく貢献します。
また、さまざまなモデルが存在しており、稲はもちろん、大豆や麦などの穀物にも対応できます。活用の幅が広がったことで、日本だけでなく世界中で重要視される農業機械へと発展してきました。
本記事では、コンバインの基本構造や作業の流れについて解説します。
コンバインの基本構造と役割
- 基本構造
まずは、コンバインがどのようなメカニズムで作物を効率よく収穫しているのか、その基本を知ることが大切です。
コンバインは大きく分けて、刈取り部・搬送部・脱穀部・選別部・排出部といった複数の要素で構成されます。これらの要素が連動することで、畑や田んぼで刈り取った作物をスムーズに脱穀・選別し、一時的に籾を貯蔵することが可能になります。例えば、刈取り部では正確に作物を刈り込み、搬送部を通して脱穀部へと運び、そこで籾と藁などの不要物が分離される流れが一体となって進みます。
脱穀後のゴミや藁くずは排出部で処理あるいは排出され、きれいになった籾はグレンタンクに集められます。これにより、次々と収穫作業を続けられるため、作業効率が格段にアップするのです。常に機械内部で作物が流れるように設計されている点が、コンバインの効率化を支える最大のポイントとなります。
作物の種類や作業条件に合わせた設定を行うことで、取りこぼしや籾の品質低下を抑えながら、安定して高い収量を得られます。特に稲作では、収穫時期を逃さずに一気に刈り取りと脱穀ができるため、天候リスクなどを最小限に抑えられるのもメリットです。
さらに、自動化や高性能センサーが発達している最新のコンバインでは、収量や水分量などを同時に測定しながら収穫することもできます。これにより、より精密な農業経営やデータ分析が進められるようになりました。
- 役割と必要性
コンバインの最大の役割は、収穫作業の時間と労力を大幅に削減できる点にあります。刈取り・脱穀・選別を一度に行ってくれるため、スピーディーかつ安定した作業が可能になります。特に高齢化や担い手不足が深刻化している農業分野では、コンバインの導入が生産性向上に直結する重要なポイントです。
さらに、一体型で作業を行うことで、収穫時に籾に混ざる不要物の量を減らすことができます。これによって、後工程の乾燥や籾摺り作業時にムダが減り、最終的に品質の高い米や穀物を得やすくなります。
- 刈り取り部の仕組み
収穫作業の第一工程を担うのが刈り取り部です。ここでは、前方の刈取刃が作物を一定の長さで切り揃え、円滑に搬送部へ送り出せるように作物を保持しながら刈り取ります。
刈り取り部が正確な高さを保つことで、必要以上に茎や葉を巻き込むことを防ぎ、脱穀作業の効率や籾の品質を落とさないよう工夫が凝らされています。また、地面との距離をこまめに調整できるモデルもあり、作物の倒伏や地形の凸凹に対応しやすくなっています。
また、刈り取り精度を高めるためには、刃のメンテナンスや適切な作業速度の設定が欠かせません。特に刃の磨耗が進むと切れ味が悪くなり、根元付近の刈り残しが増えるため、結果的に脱穀時にロスが大きくなってしまう点に注意が必要です。
①構造と役割
刈取り部はスライドする刈取刃と、収穫物をスムーズに送り込むためのオーガやベルトなどで構成されています。作物を切断するだけでなく、絡まった茎や葉を整えつつ搬送部に送り込みやすくするのが主な役割です。
オーガは螺旋状の構造を持ち、刈り取った作物を中央に集めるように働きます。一方、ベルトなどの搬送機能は、作物が乱れたり詰まったりしないよう、一定のペースで脱穀部へ運ぶためのものです。
こうした複数の要素が連動することで、作業速度を上げても詰まりにくくなり、刈取りから脱穀までを連続して行う効率が高まります。
②作物に応じた適応性
コンバインは稲だけを対象にしているわけではなく、大豆や麦など、さまざまな穀物に対応できるよう設計されています。一部の機種では専用のアタッチメントや設定変更により、異なる作物にも合わせやすいのが特徴です。
例えば、稲と大豆では植物の高さや茎の硬さが異なるため、刈取りの高さや刃の設定を細かく調整することで最適な収穫を行います。専用の装置を使えば、茎が太い作物でも詰まりにくくなるなど、収穫時の安定性を確保できます。
このように、作物ごとにカスタマイズする余地があるため、農家の生産スタイルや地域特有の作物案件にも柔軟に対応が可能です。
③搬送部と脱穀部の仕組み
刈取り部で刈り取られた作物は、搬送部を通して脱穀部へと移動します。搬送チェーンやベルトなどによって、一定の速度で作物が運ばれ、脱穀部の入口へスムーズに流れ込むように設計されています。
脱穀部に入った作物は、高速で回転するこぎ胴とこぎ歯によって、穂先から籾をはぎ取られます。取り外された籾は受け網を通過し、さらに風選や揺動板などの選別機構でゴミや藁くずが取り除かれていきます。
詰まりが起きにくいように、搬送部と脱穀部の回転速度を自動的に制御するモデルもあります。これにより、収穫効率の向上だけでなく、機械への負担も抑えられ、故障リスクの低減にもつながります。
④選別と排出のプロセス
脱穀を終えた後の最終工程として、選別と排出が行われます。選別では風選や振動を使って、籾と不要な殻や茎の切れ端などをしっかり区別します。
籾がきれいに分離されたら、排出部からゴミや余剰な藁などが排出され、主要な収穫物としての籾はグレンタンクや籾袋へと運ばれます。この区別を正確に行うことで、後の乾燥施設や籾摺り工程で手間が減り、機械トラブルを起こしにくくする効果も得られます。
コンバイン作業の流れと効率化

次に、実際の収穫作業がどのように進行するのか、各工程のポイントや効率化につながる方法を説明します。
刈取りから脱穀、選別までを一連の作業として考える時、スムーズに進むほど品質と収量、そして作業効率の向上につながります。作業速度と刈り取り部・脱穀部の動作をバランスよく保ち、最適化することが肝要です。
また、圃場(ほじょう)の状況を十分に把握し、倒伏した稲や泥が多い場所では運転速度や刈取り高さを調整することも重要です。そうすることで余計な負荷が機械にかからず、お互いに最良のパフォーマンスを持続できます。
このように作業の流れを整理することで、コンバインのポテンシャルを最大限引き出すことができます。刈取、脱穀、選別を確実に行うための各工程を理解しておきましょう。
- 収穫工程の基本
まず、田んぼに入ったコンバインが作物を刈り取る段階では、刈り取り高さをその作物に合わせて設定することが基本となります。稲の場合は倒伏していればやや低め、大豆のように茎が硬く高い作物なら上部を中心に刈り取るなど、現場の状況によって調整が必要です。
刈り取りと同時に、茎や葉の状態が悪い箇所を無理に引き込むと搬送部で詰まりが発生しやすくなります。そのため、草丈のばらつきや泥の付着度合いなどを観察しながら、刈り取り速度を柔軟に変化させることも大切です。
刈り取った後は搬送部を通し、脱穀部へ作物が運ばれます。ここで不具合や詰まりが起きると脱穀時にロスが増えたり、機械損傷の原因になるので、収穫前に搬送部の動作確認を怠らないことが基本です。
①刈り取りから搬送まで
刈り取りから搬送までの工程は、コンバインの稼働効率を左右する重要な部分です。刈り取り部では作物を確実に切り取り、搬送に差し支えないサイズと形状に整えた状態で次の工程へ渡します。
搬送部では、コンベアやチェーンなどが一定のテンポで刈り取られた作物を脱穀部へ送ります。作物が絡まったり、詰まらないよう振動や流れを制御する仕組みを備えたモデルもあります。
この区間でロスが発生しにくくするためには、刈取刃と搬送装置の定期的な潤滑や清掃が欠かせません。調整をしっかり行うことで、刈取りのスピードと搬送のリズムを合わせやすくなり、スムーズに作業が進められます。
②脱穀と籾の分離

搬送部から脱穀部へ到達した作物は、こぎ胴による高速回転で籾を分離されます。ここで重要なのは、こぎ胴やこぎ歯の回転速度と風選設定のバランスです。
スピードを速くしすぎると籾の破損や過度な振動が起こりやすく、遅すぎると処理スピードが低下して作業時間が長引くだけでなく収量にも影響が出る恐れがあります。機種の仕様や作物の状態に合わせた設定が肝心です。
脱穀後の籾は選別工程で藁やゴミが取り除かれ、グレンタンクへ蓄えられます。必要に応じてこまめにタンクを空にすることで、連続稼働が途切れにくくなり、効率的な収穫作業が実現します。
- ロス削減と収量管理のポイント
ロス削減のためには、適切な刈り取り高さと搬送速度の調整、そして脱穀部の設定が重要です。例えば、作物に合わせて刈取り部の高さを微調整することで、根元部分を無駄に刈りすぎず、落穂のリスクを減らすことができます。
また、複数のセンサーが搭載されているモデルでは、穂の量や作物の状態を感知しながら自動制御が行われる場合もあります。こうした仕組みは人手の負担を減らし、経験の浅いオペレーターでも一定の品質で収穫操作を行える点がメリットです。
収量管理の精度を高めるためには、脱穀後にどれだけの籾が正しく選別されているかもチェックする必要があります。グレンタンク内の籾を定期的に確認すると、作業中に設定の見直しが行いやすく、より安定した収量を確保できます。
- 作業効率を高める設定方法
作業効率を高める最も基本的な手段は、機種ごとの最適操作速度とエンジン回転数を把握することです。マニュアルやメーカーの推奨値を参照しつつ、圃場のコンディションや作物の倒れ具合も考慮して運転速度を調節します。
刈取り高さのセンサーが搭載されている機種では、自動調整機能を活用すればオペレーターの負担を減らしつつ、地面すれすれまで刈り取る必要があっても安全に収穫できます。
また、風選の強度や揺動板の振動レベルも設定の要となり、籾のきれいな分離と高い処理スピードの両立を目指します。適切な設定を行うことにより、ロスを抑えながら作業を素早く終わらせる事ができます。
コンバインの種類と選び方
- コンバインのタイプ
コンバインのタイプは大きく分けて普通型コンバインと自脱型コンバインがあり、それぞれ対応する作業面積や作物などが異なります。普通型はさまざまな作物に取り組む大規模農家によく使われ、自脱型は水田が多い日本の農地で特に人気があります。どちらを選ぶかは、作付けしている作物の種類や農地面積の広さ、圃場の地形などを総合的に見て判断するとよいでしょう。使い勝手とメンテナンスの面でも違いがあるため、購入前に詳細を比較することが大切です。
■普通型コンバイン
様々な穀物に対応できる汎用性の高さが魅力で、大規模農場などで重宝されます。大型でパワフルなエンジンを備えているため、大豆や麦のように稲以外の作物も効率的に収穫できます。
普通型は大型で高度な機能を搭載している一方、狭い田などでの小回りは苦手とされています。海外でも多く用いられるタイプで、多種多様な作物を一気に処理できるパワーが売りです。
■自脱型コンバイン
は日本の水田環境に特化した設計となっており、狭い農地やぬかるんだ田んぼでも作業しやすいのが特徴です。アンダートラックのクローラータイプなども多数存在し、水田に配慮した車体構造になっています。
自脱型は機体がコンパクトで、水田のぬかるみや不整地でも安定した走行が可能です。稲穂を割いて籾を取り出す独自の仕組みを持ち、籾へのダメージを抑える工夫が施されています。
- メーカー別比較
日本の主なコンバインメーカーとしては、クボタ、ヤンマー、イセキ、三菱マヒンドラ農機などが挙げられます。どのメーカーも長年の開発技術を持ち、ユーザーニーズに合わせた機能を拡充してきました。
メーカーごとに強みが異なるため、自身の作業環境や必要とするスペックに合った製品を選ぶと良いでしょう。
■クボタ
農業機械全般において日本を代表するメーカーです。コンバインでも幅広いラインナップを揃え、ユーザーの多様なニーズに応えられる体制を整えています。
メンテナンス性に優れた設計が多く、部品交換や定期点検を手軽に行えるよう配慮されています。国内にディーラー網が充実しているため、初めての導入でも安心感が高いでしょう。
大型モデルから小型モデルまで揃い、それぞれに最新の操作支援システムが導入されているのも特徴です。多彩な用途に合わせて選べる点が評価されています。
■ヤンマー
エンジン技術に強みを持ち、農業だけでなく船舶用エンジンでも有名です。そのエンジン性能を活かしたコンバインは、燃費の良さと高トルクを両立させています。
操作性に関しても評価が高く、初めてコンバインを扱う人でもスムーズに運転しやすいという声があります。
全国各地に整備拠点やサービスマンが配置されているため、急なトラブルが起きても迅速に対応できるサポート力が魅力です。
■イセキ
コンパクトな農業機械の開発に力を入れており、小規模農家でも導入しやすいサイズのコンバインを多数展開しています。操作パネルやハンドルレバーなどの配置が分かりやすく、扱いやすさを重視した設計が特徴です。
また、独自技術を採用し、高い脱穀性能と選別精度を両立させたモデルを開発しています。狭い田んぼや地形が変化に富んだ圃場でも機敏に動くため、地域特性に合わせやすい点がポイントです。
保守部品の供給や修理対応も事細かに行われており、ユーザーからは長年使用できる機械として信頼を得ています。
■三菱マヒンドラ農機
三菱グループの技術力とインドのマヒンドラ社の実績が融合して誕生したメーカーです。力強いエンジンと高い耐久性を備えた製品が特徴で、海外でも積極的に展開しています。
作業環境ごとに細かな調整ができるモデルを多くラインナップしており、実地でのユーザーテストが重視されている点も強みです。特に排藁処理がスムーズな構造を持つモデルには、リピーターからも高い評価が寄せられています。
国内ではディーラーのネットワーク整備が進んでおり、購入後のサポート体制も充実しています。これにより、故障時や点検時の連絡がスピーディーに完了し、作業からの離脱時間を短縮します。
まとめ
コンバインは、刈取り・脱穀・選別という一連の工程を一台で完結できる優れた農業機械です。基礎構造を理解し、各作業部の特徴を把握することで、より高い収穫効率を実現しやすくなります。
さらに、作業の流れやロス削減のための設定ポイントを押さえておけば、籾の取りこぼしや機械トラブルを最小限に抑えられます。また、普通型か自脱型か、あるいはメーカーごとの製品特徴を踏まえて自分の農場に合った機種を選ぶことも重要です。
コンバインを最大限に活用し、収穫作業の効率と収量をぜひ高めてみてください。
弊社は、レンタルの「ゲオ」、リユースの「セカンドストリート」をはじめ、さまざまな店舗を全国で1900店舗超を運営するリユース業界売上No.1の企業グループです。
築き上げた国内・海外の強固な販売ネットワークがあるからこそ、どんな不用品でも高価買取が可能です!
プレジャーの出張買取では、出張買取にかかる手数料・査定料がすべて無料です。
査定金額にご満足いただけない場合は、その場で無料キャンセルも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください!

